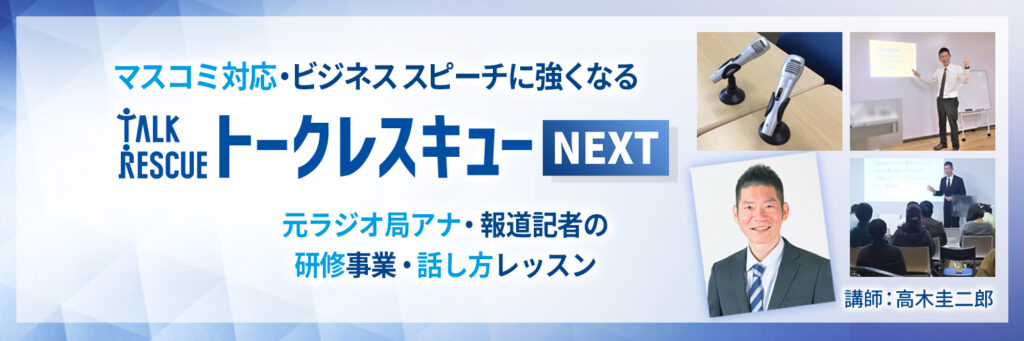この記事は当初、東日本大震災から10年の節目の2021年3月11日に公開しました。
「3.11」の記憶を風化させないために、今年この記事を再掲載します。
なお文章は大幅に加筆修正しています。(加筆修正:2024年3月11日)
―――――――――――――――――――――――――
講師の高木圭二郎です。元ラジオ局アナ・報道記者の経験から、
全国各地の自治体・公的機関で「危機管理・マスコミ対応研修」や
「情報発信力向上研修」などを行っています。
東日本大震災が発生した「3.11」の日に、この記事を書き留めたく思います。
東日本大震災、能登半島地震などで被災された皆様に
あらためてお悔みとお見舞いを申し上げます。
―――――――――――――――――――――――――
今回のテーマは「『忘れられた被災地』の災害報道」です。

(イラストはイメージ画像です)
――――――――――――――――――――――
3.11当日 停電情報対応
2011年3月11日午後、私は大規模な停電情報を伝えるため、
水戸市南町の東京電力茨城支店に車を走らせました。
当時の私はラジオ局の茨城放送に在籍。(当時の呼称はIBS茨城放送)
アナウンサー兼ディレクターの仕事から報道記者への配置転換の辞令を受けた頃でした。
3月11日午後2時46分の瞬間、私は水戸市内の自宅に居ました。
大きな揺れを感じ「これはただ事でない」とすぐさま水戸市千波町の茨城放送本社へ直行。
そこから急いで車を走らせ、大規模な停電情報を伝える業務につきました。
――――――――――――――――――――――
この時の目的地は水戸市南町の東京電力茨城支店(=当時の呼称)。
水戸市千波町の茨城放送から水戸市中心街の東京電力茨城支店までは、
通常20分~25分で着く道のりなのですが、震災の影響で道路の各地が陥没。
さらに大規模停電の影響で信号機が作動せず、私は大渋滞の中を進みました。
やっとの思いで現地入りした私は、東電茨城支店の関係者取材をした後、
携帯電話で茨城放送本社スタジオに電話。
電話での中継=「電話入り中」と呼ばれる業務で、
ここから大規模停電の現状を伝える仕事がしばらく続くこととなりました。
この時の停電世帯数は、茨城県内だけでも万単位。
そこから1か月以上にわたる災害報道を担当することになるのですが、
それは経験したことの無い長期の災害報道でした。
忘れられた被災地
「忘れられた被災地」
震災後の茨城県は、そのように呼ばれました。
東日本大震災の被害は太平洋に面する複数の県に及びましたが、
被害が大きかったのは岩手・宮城・福島の東北3県。
茨城県はこの東北3県に比べ、死者・行方不明者が少なく、
さらに福島県内で東京電力福島第一原発の事故も生じたことから、
NHKや東京キー局、大手新聞社は岩手・宮城・福島の情報を大々的に扱いました。
ニュースの放送時間や新聞の紙面には限りがあります。
東京の大手マスコミは大津波や原発事故の様子を詳しく報じ、
その結果、茨城県内のニュース量は減少。
しかし、茨城の被災状況も甚大でした。
茨城県沿岸部は津波被害を受け、県内各地で死者・負傷者も出ました。
私がいた水戸市内でも道路陥没だけでなく、建造物の甚大な被害が見られました。
生活面では震災での被災後、停電・断水が続き、ライフラインの影響も大きく
多くの方々が被災地としての生活を余儀なくされていたのです。
しかし報道各社の茨城のニュース量は少な目。
ローカルニュースを報じる県域民放テレビ局が全国の都道府県で唯一無い、
という独自のメディア事情も重なり、茨城県は「忘れられた被災地」と呼ばれていたのです。
――――――――――――――――――――――
震災から数週間が経過し、徐々に日常を取り戻し始めても、
水戸市内の物流は途絶えがちでした。
スーパーの食材はすぐに売り切れ。
辛うじて残っていた酒店のチーズ類がその日のおかず。
ガソリンスタンドもガソリン不足から給油不可、という日々がしばらく続いたのです。
災害報道を担当する私は、車のガソリンが底をついたことから、
徒歩で出社、徒歩で帰宅、という日々も送り続けました。
災害報道をする私自身が被災者の一人でもあったのです。
ラジオが見直された日々
東日本大震災後の災害報道はその後も続きました。
当時の茨城放送では通常放送をほぼ全て休止。
相次ぐ余震の情報や、ライフライン関連の情報、給水所の情報、
避難所での情報などを連日伝えていました。
それはNHKや東京キー局など、大手マスコミが伝えきれない「茨城独自の情報」でした。
取材スタッフも各地の被害状況や、復旧復興に関する動きを連日紹介。
地域密着型のラジオ局ならではの情報発信となったのです。
ラジオ局の茨城放送は、この東日本大震災の災害報道で
改めてその存在意義を見直されたのです。
――――――――――――――――――――――
被災後、茨城放送本社には「ラジオで紹介してほしい情報がある」と、
大量の電話やFAX、メールが寄せられていました。
それらの情報を送ってくださったのは、茨城県内の自治体、関係機関の他、
医療関係者、各種団体、学校関係者、企業など様々。
「ここで炊き出しを行っている」、「断水がようやく復旧」等の情報もあり、
スタッフは情報を確認したうえでラジオで紹介、という対応に追われました。
同時に、お叱りのコメントもかなり届きました。
「茨城には茨城放送しかねえ!もっといっぱい放送しろ!」などと
被災した悔しさをぶつけるようなお叱りの電話やFAXも届いていたのです。
オールドメディアのラジオ。音声だけのラジオ。茨城県域のラジオ。
普段ラジオを聞かない人たちからも、この大規模災害を通じ
「茨城放送を聞くようになった」との話も聞かれました。
震災報道を支えたディレクター
東日本大震災の災害報道の現場を経験し、私は強く実感したことがあります。
それは「スタッフ体制の整備の重要さ」です。
長期にわたる災害報道を支えたスタッフは多数。
ラジオで声を出すアナウンサー、パーソナリティ陣の存在はやはり大きいのですが、
私が不可欠と感じたのは、ディレクターら「声を出さないスタッフ」の存在でした。
災害時は情報の混乱が生じます。
震災後、私がいた放送現場ではディレクター陣が連日情報を整理・確認し、
赤ペンで重要箇所に線を引き、アナウンサーらに伝える、という地道な作業を、
延々と継続していました。これは災害報道に不可欠な業務の一つです。
イニシャル紹介になりますが、当時の茨城放送ディレクターのWさん、Yさんらは
それこそ不眠不休でスタジオ対応と資料整理を続けていたのを、私は鮮明に覚えています。
震災後は、それほどまでに大量のFAXやメールが茨城放送本社に届いていたのです。
ライフライン関連情報の資料だけも、通常はA4型のケースで1~2ケース分のところ、
資料ケースが5~10ケースに及ぶほど寄せられました。
スタジオ前のテーブルでディレクターの皆さんは、寄せられる大量のFAXや
メール情報の紙を一つずつ精査し続けたのです。
大規模災害では、情報が入り乱れます。
情報の的確な仕分けは、やはり人の力に頼るしかありません。
そして継続的な災害報道には多数のスタッフが必要になります。
長期にわたる災害報道は、スタッフ体制を整えたうえでの
「総合力」でしか乗り切れないのです。
震災後の私の見解 人的な備えの再確認を
東日本大震災から10年以上が経過し、今や情報インフラも以前よりはるかに整いました。
情報インフラの話で言えば、現代社会はSNS全盛の時代。
スマホ一つで情報発信ができ、文字情報や画像のみならず、
動画やライブでの情報配信も容易になっています。
このようなネット全盛の時代ですが、やはり放送局の情報は多くの人に信頼されます。
だからこそ放送業界の皆様は、平時から緊急時のスタッフ体制を整えるべきと私は考えます。
「スタッフ体制の整備の重要性」は、放送業界の皆様だけでなく、
災害に備える全ての皆様に知ってほしい情報です。
災害への備えは、「オモテ=対外的な部分」の対応のみならず、
「ウラ=バックオフィスの人員体制」をも考える必要があるのです。
――――――――――――――――――――――
現在、私は研修講師として自治体・公的機関向けに
「マスコミ対応・危機管理研修」などを実施しています。
講座では危機管理3原則として、「予防・備え・初動」の重要性も
説明しますが、平時の備えがなければ的確な初動対応にはつながりません。
また近年頻発する広域災害を受け、被災自治体の首長らは、
「職員を休ませること」の大切さも伝え始めています。
「職員を休ませること」の重要性については被災地首長の声として
「内閣府 防災情報のページ」などでも紹介されています。
(参考)内閣府防災情報のページ 災害時にトップがなすべきこと 関連
http://www.bousai.go.jp/kohou/kouhoubousai/h29/87/news_02.html
大規模災害時のスタッフ体制も、あえて職員を休ませることで、
組織としてシームレスな(=切れ目のない)体制を構築できるというわけです。
国は防災関連で「国土強靭化」のスローガンを掲げていますが、
皆様の職場でも「強靭化」、それも「スタッフ体制の強靭化」を
意識していただくのが良いかと思われます。。
「3.11」の節目で、多くの皆様に東日本大震災の事実を見つめなおし、
多くの「備え」につなげていただきたいと私は考えています。
そして「3.11」当時にご対応いただいた関係者の皆様、支援してくださった皆様、
多くのリスナーの皆様に改めて御礼申し上げます。
長文にお付き合いくださり、誠にありがとうございました。
以上、皆様のご参考になれば幸いです。
(講師:高木圭二郎)

この記事を書いた人
高木 圭二郎(たかぎ けいじろう)
研修講師・フリーアナウンサー トークレスキューNEXT代表
(元 茨城放送アナウンサー兼 ディレクター・報道記者)
講師プロフィール詳細はこちら
https://talkrescue.jp/instructor/profile
講師活動の実施実績はこちら。
https://talkrescue.jp/instructor/achievements
【 研修ページ ご案内 】
研修・講演プランは下記ページで紹介中。
主に自治体向け研修のページですが企業等も対応可能です。
トークレスキューNEXT マスコミ対応研修
https://talkrescue.jp/training/media_training
トークレスキューNEXT 危機管理研修
https://talkrescue.jp/training/risk_management
トークレスキューNEXT メディアトレーニング研修
https://talkrescue.jp/training/pr-media-training
トークレスキューNEXT 情報発信力研修(広報PR研修)
https://talkrescue.jp/training/public_relations
トークレスキューNEXT 説明力向上研修(プレゼン研修)
https://talkrescue.jp/training/explanation
トークレスキューNEXT 説明力向上研修【動画研修プラン】
https://talkrescue.jp/explanation-video
トークレスキューNEXT リーダーのための伝わる話し方
https://talkrescue.jp/training/speech
© 高木圭二郎 2025 All Rights Reserved.
当サイトの全コンテンツの無断転載を禁じます。
無許可の転載、複製、転用等は法律により罰せられます。